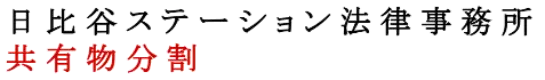所有者不明の共有土地建物ついて
~所在等不明共有者持分取得申立て及び所在等不明共有者持分譲渡権限付与決定申立て~
平成29年の国土交通省の調査によれば、所有者不明土地(不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地や、所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地)が、国土の22%もあると言われていました。そこで、政府は、所有者不明土地の対策を推進し、令和3年4月28日に民法等が改正され、令和5年4月1日に施行されました。
これまで、共有者が所在不明である場合において共有物分割請求訴訟を行う際には、不在者財産管理人の選任申立てを行う必要がありましたが、この不在者財産管理人の選任申立てには、手続上の負担や費用の負担に重いものがありました。さらに、共有者の氏名が分からないなど不特定の場合には、不在者財産管理制度も利用できず、手詰まりとなっていました。
そこで、上記民法改正によって、所在等不明の共有者がいる不動産については、他の共有者が、裁判所の決定を得て、所在等不明共有者の共有持分を取得できたり(所在等不明共有者持分取得申立て)、申立てをした共有者に、所在等不明共有者の共有持分を譲渡する権限を付与できたり(所在等不明共有者持分譲渡権限付与決定申立て)するようになりました。
所在等不明共有者持分取得申立てについて
所在等不明共有者持分取得申立てとは、共有状態にある土地や建物といった不動産について、共有者が、他の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない場合に、裁判所に対し、この所在等不明共有者の共有持分を申立人に取得させるよう求める手続です。
申立人は、所在等不明共有者の共有持分を取得する代わりに、その共有持分の時価相当額を供託しなければなりません。そのため、申立人は対象不動産の不動産鑑定書や簡易鑑定書を提出して、その時価相当額を供託するために資金を用意する必要があります。
ただし、所在等不明共有者の持分が、共同相続人間で遺産分割をすべき相続財産に属する場合には、直ちに申し立てることができず、相続開始から10年以上経過していることが必要です(民法262条の2第3項)。
申立人は、対象となる共有不動産について持分を有する共有者に限られますので(民法262条の2第1項)、共有者ではない第三者が所在等不明共有者持分取得の申立てを行うことはできません。また、申し立てる裁判所は、対象となる不動産の所在地を管轄する地方裁判所になります(非訟事件手続法87条1項)。
裁判所は、申立てがあった後、この申立てがあった旨及び所在等不明共有者は異議があるときはその旨の届出をすること等を公告し、かつ、所在等不明共有者以外の他の共有者に対しても同様に通知します(非訟事件手続法87条2項3項)。この異議届出期間は3ヶ月を下ってはならないとされています。この異議届出期間において、所在等不明共有者からの届出がなされたときには、申立ては却下されることになります。
3ヶ月以上の異議届出期間が届出なく経過した場合には、裁判所は具体的な供託金額を決定して供託命令を下します。申立人が供託を行うことにより所在等不明共有者の持分の取得の裁判がなされ、この裁判が確定したときに、申立人は所在等不明共有者の持分を取得することになります(非訟事件手続法87条9項)。
所在等不明共有者持分譲渡権限付与決定申立てについて
所在等不明共有者持分譲渡権限付与決定申立てとは、共有状態にある土地や建物といった不動産について、共有者が、他の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない場合に、裁判所に対し、この所在等不明共有者以外の共有者全員が第三者に対して持分全部を譲渡することを条件に、所在等不明共有者の持分をその第三者に譲渡する権限を申立人に与えるよう求める手続です。不動産の共有持分のみを売却する場合よりも、不動産全体を売却して、持分に応じて売却代金を配分した方が高額になることが多いことから、所在等不明共有者がいる場合でも不動産全体を売却できるようにしています。
申立人は、所在等不明共有者の共有持分の譲渡権限を付与される代わりに、その共有持分の時価相当額を供託しなければなりません。そのため、申立人は対象不動産の不動産鑑定書や簡易鑑定書を提出して、その時価相当額を供託するために資金を用意する必要があります。
ただし、所在等不明共有者の持分が、共同相続人間で遺産分割をすべき相続財産に属する場合には、直ちに申し立てることができず、相続開始から10年以上経過していることが必要です(民法262条の3第2項)。
申立人は、対象となる共有不動産について持分を有する共有者に限られますので(民法262条の3第1項)、共有者ではない第三者が所在等不明共有者持分譲渡権限付与決定の申立てを行うことはできません。また、申し立てる裁判所は、対象となる不動産の所在地を管轄する地方裁判所になります(非訟事件手続法88条1項)。
裁判所は、申立てがあった後、この申立てがあった旨及び所在等不明共有者は異議があるときはその旨の届出をすること等を公告します(非訟事件手続法88条2項、87条2項1号2号4号)。この異議届出期間は3ヶ月を下ってはならないとされています。
3ヶ月以上の異議届出期間が届出なく経過した場合には、裁判所は具体的な供託金額を決定して供託命令を下します。申立人が供託を行うことにより所在等不明共有者の持分譲渡権限付与の裁判がなされ、この裁判が確定したときに、申立人は所在等不明共有者の持分の譲渡権限を取得することになります(非訟事件手続法88条2項、87条9項)。
所在等不明共有者の持分譲渡は、裁判が確定しただけでは足りず、別途不動産を購入する第三者と売買契約を締結して譲渡することが必要ですが、この譲渡は裁判確定の日から2ヶ月以内にしなければなりません(非訟事件手続法88条3項)。ただし、この期間は、裁判所において伸長することができます(非訟事件手続法88条3項但書)。
所有者不明の共有土地建物がある方へ
所有者不明の共有土地建物ついて、どのように進めるべきか総合的に検討した上で対応いたしますので、お気軽にご相談ください。 03-5293-1775